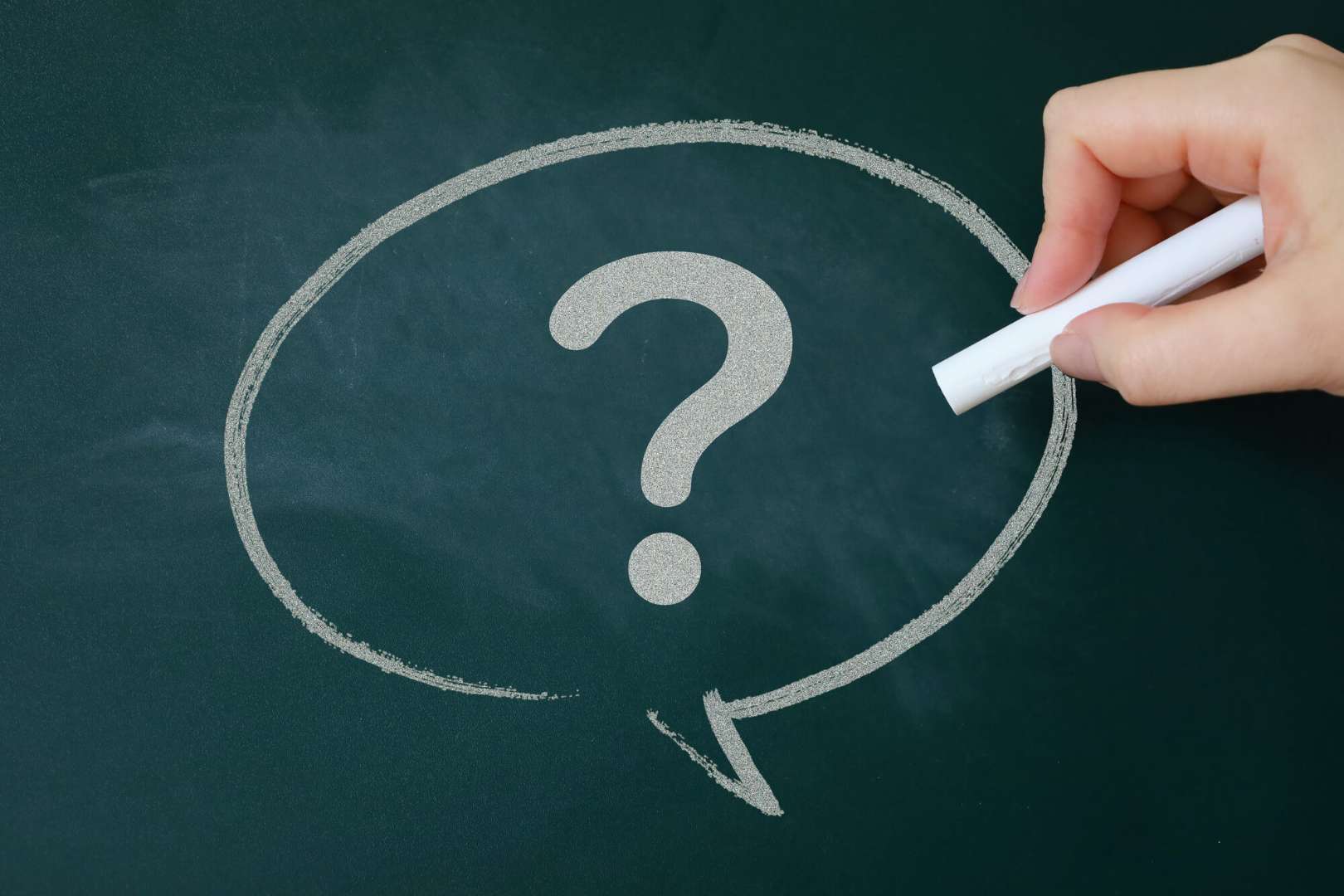「第二種電気工事士はやめとけ」「きついだけで将来性がない」。これから資格を取ろうと考えている方や、キャリアを歩み始めたばかりの時に、そんな言葉を耳にして不安な気持ちになっていませんか。高い志を持って目指している道だからこそ、ネガティブな評判はことさら心に重くのしかかるものです。
なぜ、こうした言葉が生まれるのでしょうか。その背景には、電気工事という仕事が持つ、紛れもない厳しさがあります。体力が求められる場面も、常に安全への高い意識が必要な緊張感も、決して楽なことばかりではないのは事実です。この先では、そうした厳しい側面から目をそらすことなく、まずは「やめとけ」と言われるリアルな理由を正直にお伝えします。
しかし、それは物語の半分に過ぎません。多くの技術者たちが、その厳しさを乗り越えてなお、この仕事に誇りを持ち、日々の現場に立ち続けているのもまた、確かな現実なのです。
この記事が、一方的な情報であなたの決断を揺さぶるのではなく、業界の光と影の両方を知った上で、ご自身の目で本質を見極め、心から納得のいく道を選ぶための、誠実な羅針盤となることを願っています。
なぜ彼らは「やめとけ」と言うのか?5つのネガティブな本音
「やめとけ」という言葉には、実際にこの仕事に携わった人が感じた、偽りのない本音が込められていることがあります。まず、その声に真摯に耳を傾け、電気工事士という仕事が内包する厳しさについて、一つひとつ見ていきましょう。
1. 夏は暑く、冬は寒い。身体で感じる厳しさ
電気工事の現場は、快適なオフィスの中だけとは限りません。建設途中の建物では、夏はうだるような暑さの中で汗を流し、冬は凍えるような寒さの中で手を動かします。時には、狭くて暗い天井裏や床下での作業、足場の悪い場所での作業も求められます。こうした環境で一日中身体を動かすことは、相応の体力が求められる、紛れもない事実です。
2. 「絶対」が求められる安全へのプレッシャー
電気を扱う仕事は、常に危険と隣り合わせです。感電や漏電、あるいは高所からの転落など、一瞬の気の緩みが取り返しのつかない大事故に繋がる可能性があります。だからこそ、現場では常に高い集中力と、「安全が最優先」という強い意識が求められます。この絶え間ない緊張感が、精神的な負担となってしまうと感じる人も少なくありません。
3. 一度覚えたら終わりではない、学び続ける大変さ
電気に関する技術や法律は、日々進化し、変化しています。新しい工法や新しい素材が登場すれば、その知識を学び直さなければなりません。省エネや再生可能エネルギーに関する新しい法律が施行されれば、それに対応する必要も出てきます。「資格を取ったら終わり」ではなく、プロとして働き続ける限り、常に新しい知識を吸収し続ける勉強熱心さが求められるのです。
4. 責任の重さと給与が見合わないと感じる現実
社会のインフラを支えるという責任の重い仕事であるにもかかわらず、働く会社によっては、その大変さに見合った給与が得られていないと感じるケースがあるのも事実です。特に経験の浅い時期は、覚えることの多さや仕事の厳しさに対して、収入が物足りないと感じてしまうことがあるかもしれません。
5. 職人気質の文化と人間関係
建設業界には、昔ながらの「職人気質」の文化が根強く残っている現場も存在します。「仕事は見て盗め」という厳しい指導や、元請けの会社や他の専門業者との間での、簡単ではないコミュニケーションに悩むこともあります。こうした人間関係が、仕事そのものよりも大きなストレスの原因となってしまうこともあるのです。
デメリットの裏側にある、AI時代にも色褪せない専門職としての「真価」
セクション2で触れたような厳しい現実は、確かに存在します。しかし、もし本当にデメリットしかない仕事であれば、今頃、電気工事士という職業は担い手がいなくなっているはずです。それでもなお、多くの人々がこの仕事に誇りを持ち、自らの使命として日々の現場に向かうのはなぜでしょうか。それは、厳しさの裏側にある、それを上回るほどの大きな「価値」と「やりがい」があるからです。
1. 社会を支える「誇り」と「使命感」
私たちの暮らしは、電気がなければ一日たりとも成り立ちません。家庭の明かりやスマートフォンの充電はもちろん、社会全体を動かす交通機関、オフィス、病院、工場。そのすべてが、電気が安定して供給されることで機能しています。電気工事士は、その大動脈とも言えるインフラを、自らの手で築き、守る仕事です。スイッチを入れた時に明かりが灯る、あの「あたりまえ」を創り出しているという実感。人々の生活に直接貢献できるという手応えは、他では決して味わうことのできない、大きな誇りとなります。
2. 人の手でしかできない「なくならない仕事」
AIやロボット技術がどれだけ進化しても、電気工事の仕事が完全になくなることはないでしょう。なぜなら、一つとして同じ現場はなく、その場その場の状況を的確に判断し、配線を施し、機器を接続する、といった繊細な作業は、人間の柔軟な思考力と巧みな手作業が不可欠だからです。時代に左右されない「手に職」を持つことは、変化の激しい現代において、何にも代えがたい大きな強みとなります。
3. 経験が拓く「キャリアの多様性」
電気工事士としてのキャリアは、現場作業員として終わるわけではありません。経験を積み、第一種電気工事士や施工管理技士といった資格を取得すれば、より大きな現場の責任者としてプロジェクト全体を動かす立場になることもできます。また、十分な実力と人脈を築けば、独立して自分の会社を立ち上げるという道も拓けます。自分の努力と実力次第で、未来の可能性をどこまでも広げていける。それも、この仕事が持つ大きな魅力の一つなのです。
結論は「会社次第」。後悔しないための職場選びの分岐点
これまで見てきたように、電気工事士という仕事には厳しい側面と、それを上回る大きなやりがいが存在します。では、なぜある人は「やめとけ」と言い、ある人は「誇りだ」と言うのでしょうか。その決定的な違いは、個人の能力や適性だけの問題ではありません。結論から言えば、それは「働く会社がどのような環境か」によって、ほぼ決まると言っても過言ではないのです。あなたの未来が、疲弊してしまう「きつい現場」になるか、やりがいに満ちた「成長の舞台」になるか。その分かれ道となる、職場選びの視点について解説します。
安全への考え方:「個人の注意」か「組織の仕組み」か
事故が起きた時、「本人の注意不足だ」と個人の責任で終わらせてしまう会社があります。一方で、事故を未然に防ぐために、会社全体で安全教育に時間をかけ、危険な作業を予測し対策を立てる活動を徹底し、必ずチームで声を掛け合いながら作業を進める、といった「仕組み」で安全を守ろうとする会社もあります。あなたの命と健康を守るという、最も基本的な姿勢に、企業の品格が表れるのです。
人材への考え方:「使い捨ての駒」か「育てる財産」か
人手不足を補うためだけに人を採用し、十分な教育もせずに現場に送り出す会社では、技術はなかなか身につきません。やがて自信を失い、仕事が嫌になってしまうのも無理はないでしょう。その反対に、社員を未来への「財産」と考え、時間をかけて一人前のプロに育てようとする会社もあります。体系的な研修制度を設け、先輩が後輩を丁寧に指導する文化が根付いている。そんな環境こそが、あなたの成長を確かなものにしてくれます。
チームのあり方:「孤立した個人」か「支え合う仲間」か
建設現場では、様々な専門家が協力して一つのものを作り上げます。しかし、職場によっては連携がうまくいかず、職人同士が孤立し、分からないことがあっても気軽に聞けない、という雰囲気のところもあります。一方で、困難な現場であるほど、部署の垣根を越えて知恵を出し合い、困っている仲間がいれば自然に助け合う、そんなチームワークを大切にする会社も存在します。仕事の厳しさを乗り越える力は、個人の能力だけでなく、こうした仲間との繋がりから生まれるのです。
「社員第一主義」の企業は、不安をどう乗り越えているのか?
「社員を大切にする会社が良いのはわかるけれど、具体的にどんな会社なのだろう」。そう思われる方もいるかもしれません。ここでは、「やめとけ」と言われる理由として挙げられた様々な不安を、企業努力によって「働きがい」へと転換している、具体的な事例を見ていきましょう。
例えば、社会の重要な電気インフラを数多く手掛けるスバル電業社では、「社員第一主義」という考え方を何よりも大切にしています。彼らが実践する取り組みは、「やめとけ」という言葉の背景にある不安を乗り越えるための、確かなヒントになるはずです。
「安全」への不安を、徹底した仕組みで「安心」へ
同社では、個人の注意だけに頼るのではなく、組織全体で安全を守る文化が徹底されています。作業前には必ずチーム全員で危険予知活動を行い、潜んでいるリスクを共有します。また、経験の浅い技術者が一人で危険な作業を行うことは決してなく、常に経験豊富な先輩とチームを組むことで、互いにフォローし合いながら作業を進めます。こうした幾重もの仕組みが、「危ない」という不安を「今日も安全に働くことができる」という日々の安心感に変えているのです。
「学び」への不安を、独自の教育制度で「成長」へ
「学び続けるのが大変」という不安に対しても、同社は明確な答えを用意しています。それが、独自の教育機関「スバル・ユニバーシティ」です。ここでは、電気の基礎知識から専門的な技術まで、未経験者でも段階的かつ体系的に学べるプログラムが組まれています。もちろん、第一種電気工事士や施工管理技士といった上位資格の取得も、費用面を含めて会社が全面的に後押しします。学びの不安は、確かな成長を実感できる喜びに変わります。
「人間関係」への不安を、チームワークで「誇り」へ
同社が特に重視するのが、社員同士の繋がり、すなわちチームワークです。一人では乗り越えられないような困難な現場であっても、仲間と知恵を出し、助け合い、励まし合うことで乗り越えていく。その過程で生まれる一体感と、プロジェクトを成し遂げた時の大きな達成感が、仕事への誇りを育みます。厳しいだけでなく、共に笑い合える仲間がいる。それが、仕事を続けていく上での何よりの支えとなるのです。
https://www.subarudengyo.co.jp/recruit
他人の「やめとけ」に惑わされない。あなたが働く「意味」を見つけよう
ここまで、「第二種電気工事士はやめとけ」という言葉の裏にある真実と、その言葉を乗り越えるための視点についてお伝えしてきました。
「やめとけ」という言葉は、決して嘘やデタラメではありません。しかしそれは、あくまで特定の環境や個人の経験から生まれた、業界の一側面を切り取った意見に過ぎない、ということもご理解いただけたかと思います。その言葉に過度に惑わされ、あなたが抱いた大切な志まで諦めてしまう必要はどこにもありません。
本当に大切なのは、他人の評価に振り回されるのではなく、あなたが仕事を通して何を実現したいのか、どんな技術者になりたいのかという「あなた自身の軸」を持つことです。
電気工事士という仕事は、ただ配線をつなぐだけの作業ではありません。人々の「あたりまえの暮らしを、あたりまえに実現する」という、大きな社会的使命を担っています。厳しい仕事の先には、社会に貢献しているという確かな手応えと、自分の仕事が誰かの生活を支えているという静かな誇りがあります。
もしあなたが、単に技術を身につけて収入を得るだけでなく、その技術で誰かの役に立ちたい、仲間と共に成長する喜びを感じたいと願うなら、その気持ちこそが、あなただけの「働く意味」になるはずです。